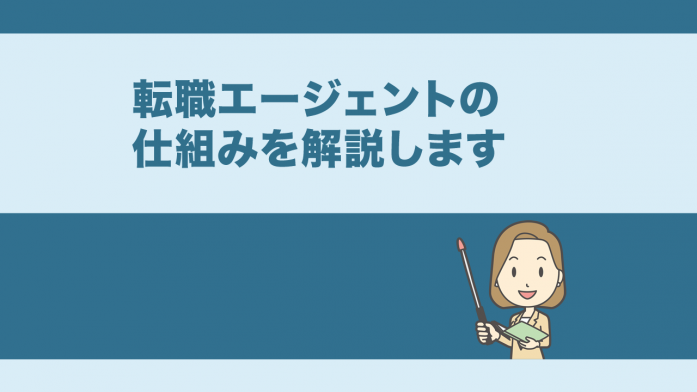転職エージェントをはじめて利用する方に、転職エージェントの仕組みを9つの項目から解説していきます。
- 転職エージェントの仕組みを教えて!
- 転職エージェントの転職支援サービスって、どんなサービス?
- キャリアアドバイザーって、何をしてくれるの?
- 転職エージェントが紹介してくれる求人には、どんな特徴がある?
- 転職エージェントは、どうして無料で使えるの?
はじめて転職エージェントを使う時は、わからないこと、気になることがたくさん出てきます。
この記事を読めば、転職エージェントが提供する転職支援サービスの内容が、裏事情も含めて網羅的にわかり、安心して転職エージェントが利用できるようになるはずです。
目次
- 1 【仕組み解説1】転職エージェントが提供する転職支援サービスとは?
- 2 【仕組み解説2】転職エージェントが紹介する求人の特徴とは?
- 3 【仕組み解説3】転職エージェントのキャリアアドバイザーとリクルーティングアドバイザーの役割は?
- 4 【仕組み解説4】転職エージェントの運営体制は?
- 5 【仕組み解説5】転職エージェントの利用方法、利用の流れは?
- 6 【仕組み解説6】転職エージェントを利用するメリットは?
- 7 【仕組み解説7】転職エージェントを利用するデメリットとは?
- 8 【仕組み解説8】転職エージェントが無料で利用できる仕組みとは?
- 9 【仕組み解説9】転職エージェントに利用を断られることがあるの?
- 10 あとがき:転職エージェントの仕組み【無料の理由、転職支援の内容など裏事情を含む9項目から解説】
【仕組み解説1】転職エージェントが提供する転職支援サービスとは?
転職エージェントは、転職したい人(求職者)と、社員・職員を採用したい企業や組織との間を取りもち、転職を支援するサービスです。
このサービスは転職支援サービス、人材紹介サービス、職業紹介サービスとも呼ばれ、このサービスを運営する企業を人材紹介会社、職業紹介事業者と言います。
求職者が経歴や実績、スキル・技術、希望を伝えると、転職エージェントの担当者は求職者にぴったりの求人を探して紹介し、転職が決まるまで転職相談、自己PR・志望動機や履歴書・職務経歴書作成のアドバイス、求人企業への推薦、面接対策、待遇交渉などで転職活動をサポートしてくれる便利なサービスで、無料で利用できます。
- 求職者に対する転職エージェントのサービス
-
- 転職エージェントは、求職者の求職の申し込みを受け付けます。
- 求職者の経歴や実績、スキル・技術、希望にマッチする求人を、求職者に紹介します。
- 求職者が転職したいと思うような求人が見つかれば、面接を設定します。
- 企業や組織に対する転職エージェントのサービス
-
- 転職エージェントは、企業や組織(求人者)の求人の申し込みを受け付けます。
- 求人の仕事内容、人材要件にマッチする求職者に求人を紹介して、求人に応募する求職者を求人者に紹介します。
- 求人者が採用したいと思うような求職者が見つかれば、面接を設定します。
転職エージェントという事業の中で、特に重要になってくるのが情報です。求職者、求人企業には、それぞれ希望や要件があります。
転職エージェントはこの希望、要件といった情報を活用して、求職者と求人企業との間を取りもち、より良い雇用関係がうまれることを目指します。
ちなみに、法律では転職支援サービスのことを職業紹介といい、職業安定法(第4条第1項)では、次のように定義しています。
この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
転職エージェントをはじめとする職業紹介事業は、誰でも運営できるわけではありません。運営するには、厚生労働省(厚生労働大臣)の許可が必要となります。
【仕組み解説2】転職エージェントが紹介する求人の特徴とは?
転職エージェントは、さまざまな業種、職種、地域の求人を紹介してくれます。一方、あつかう求人の雇用形態は正社員が中心で、契約社員の求人が一部あり、パート・アルバイト、派遣の求人はほとんどありません。
求職者が希望条件を転職エージェントに伝えると、希望にあう求人を探し出し、紹介してもらえます。紹介される求人の中には、転職エージェントに登録することではじめて紹介してもらえる非公開求人もあります。
- 非公開求人
-
非公開求人は、社員・職員を採用したい企業や組織が、公に募集していない求人です。転職エージェントを利用することで紹介してもらえる求人で、転職エージェントが保有する求人のうち50〜80%が非公開求人になります。求職者の経歴やスキル、希望条件などが、採用したい企業や組織の条件、要件に合致する場合、転職エージェントから求職者に非公開求人が紹介されます。
求人を非公開にする理由や背景には、次のようなものがあります。
- 急いで経験やスキルがある人物を採用したい
- 社内で人材を育成する時間、能力がない
- 社内外に秘密裡に採用活動を進めたい
- 中途採用業務を転職エージェントに一任し省力化をはかりたい
その他にも、企業と特定の転職エージェントの間に太いパイプがあって、中途採用業務をアウトソーシングの形で一任されている転職エージェントもあり、このようなケースでは求人が公開されることはほとんどありません。
また、転職エージェントは、豊富な求人情報量も魅力の一つです。
例えば、業界最大手の転職エージェントであるリクルートエージェントが保有する求人数(公開求人と非公開求人の合計)は、1,015,297件にも上ります(2025年7月2日時点)。
転職エージェントのキャリアアドバイザー(求職者の担当者)は、求職者の経験やスキル、希望条件を把握したうえで、求人企業が求める要件・要望を踏まえ、多数の求人の中から求職者に最適なものを選び、紹介してくれます。
【仕組み解説3】転職エージェントのキャリアアドバイザーとリクルーティングアドバイザーの役割は?
大手の転職エージェントの担当者は、求職者の転職活動を支援するキャリアアドバイザーと、企業や組織の採用活動を支援するリクルーティングアドバイザーに分かれています。
求職者が接することになるのは、キャリアアドバイザーです。
キャリアアドバイザーは、求職者の転職支援を担当する人材紹介会社の社員です(コンサルタント、キャリアパートナーなど別の呼称を使う人材紹介会社もあります)。
キャリアコンサルタントという名称もありますが、キャリアコンサルタントはキャリアコンサルティングの国家資格を持つ人だけが名乗れます(参考:厚生労働省「キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント」)。キャリアコンサルタントの資格を持つ、人材紹介会社の社員もいます。
なお、中規模・小規模の転職エージェントの担当者は、キャリアアドバイザーとリクルーティングアドバイザー両方の役割を兼務しているケースもあります。
ここでは、大手転職エージェントのキャリアアドバイザー、リクルーティングアドバイザーの役割をご紹介します。
キャリアアドバイザーの役割
キャリアアドバイザーの仕事は、次の通りです。
- 転職エージェントのキャリアアドバイザーの仕事
-
- 求職者の経験・スキルや希望の確認
- 求職者の転職、キャリアデザインに関する相談
- 求職者への転職に関する情報提供、求人企業の紹介
- 求職者の応募書類や面接、退職に関する助言
- 求職者の面接日、入社日、待遇面の要望確認
求職者はキャリアアドバイザーとの対面形式の面談、電話、メール等によってコミュニケーションを取りながら、転職活動を進めます。
キャリアアドバイザーとコミュニケーションを活性化させ、信頼関係を構築することが、転職活動を円滑に進めるにあたり肝となります。
滅多にあることではありませんが、相性が悪いキャリアアドバイザーが担当になってしまうこともありえます。
大手の転職エージェントでは、万が一このような問題が起こってしまった時の対策として、利用者の希望によりキャリアアドバイザーを変更できる制度を設けています。実際に利用することは先ずない制度ですが、このような制度があれば安心につながりますね。
中規模・小規模の転職エージェントでは、担当者そのものが少なく、担当者を変えられるところは多くありません。
転職エージェントのキャリアアドバイザーについては次の記事にも書いていますので、あわせてご覧ください。
リクルーティングアドバイザーの役割
リクルーティングアドバイザーの仕事は、簡単に言うと求人企業の営業担当者です。
- 転職エージェントのリクルーティングアドバイザーの仕事
-
- 求人企業への定期訪問、情報収集
- 求人企業の新規開拓
- 求人企業の求人票作成
- 求人企業への人材紹介、応募手続き
- 求人企業との面接日、入社日、待遇面等の調整・交渉
求人企業への応募手続きは、リクルーティングアドバイザーを介して行われ、リクルーティングアドバイザーは求職者の応募書類を確認し、求人企業の要件・要望を満たさない求職者をふるいに掛けることもあります。転職エージェントの裏事情のようなお話ですが、ご存知ない方も多いようなので知っておいてください。
リクルーティングアドバイザーと求職者が、顔をあわせる機会は少ないと思います。私がこれまでリクルーティングアドバイザーと会ったのは、内定が出た直後、内定を辞退した時、転職を決心した時ぐらいです。
このように求人企業に対して、お金を請求できるか否か大きな影響をおよぼすタイミングで、リクルーティングアドバイザーが登場することが多いようです。
【仕組み解説4】転職エージェントの運営体制は?
一般的に、転職エージェントは、企業規模で社内体制、対応領域が変わってきます。ここでは転職エージェントの運営体制を解説します。
分業制の転職エージェントと両面制の転職エージェント
大手の転職エージェントでは、前述したキャリアアドバイザー、リクルーティングアドバイザーのように、求職者と求人企業の担当者が分かれています。これを分業制と呼んでいます。
一方、中規模・小規模の転職エージェントでは、求職者と求人企業の担当者を兼務することが多い傾向にあります。これを両面制と呼んでいます。
例えば、社長1人だけで社員がいない転職エージェントもあり、このような企業の社長は、必然的に求職者と求人企業の担当者を兼務しなければなりません。
なお、大手転職エージェントの中でも、エグゼクティグ・管理職などのハイクラス層の人材紹介を専門とする部署では、両面制となっているケースは珍しくありません。
次に、求職者の立場から、分業制と両面制の長所、短所を見てみましょう。
| 長所 | 短所 | |
|---|---|---|
| 分業制 | +担当者は求職者に集中し、求職者優先で対応する +紹介してもらえる求人の範囲が広く、量が多い | +担当者は求人企業と接点が少なく、求人企業を深く知らない +社内の情報共有が不足すると、紹介される求人のミスマッチが起こりやすくなる |
| 両面制 | +担当者は求人企業と接点が多く、求人企業を深く知っている +担当者から紹介される求人に、ミスマッチが少ない | +担当者は、求職者と求人企業のバランスを取りながら対応する +紹介してもらえる求人の範囲が狭く、量が少ない |
分業制の長所と短所を裏返せば、両面制の長所と短所になります。
求職者が手厚いサービスを受けられるのは分業制のように見えますが、分業制ではキャリアアドバイザーとリクルーティングアドバイザーの緊密な連携、情報共有が必須となり、これができないと提供するサービスレベルは低下します。
総合型の転職エージェントと特化型の転職エージェント
次に転職エージェントがあつかう求人の対応領域から、大手の転職エージェント、中規模・小規模の転職エージェントの違いを確認します。
大手の転職エージェントでは様々な業種、職種、年代、地域の求人をあつかっています。これを総合型と呼んでいます。
大手の転職エージェントでは、IT、金融、製造などの業種か、人事、エンジニア、営業などの職種ごとに、社内の組織を編成していることが多いです。
一方、中規模・小規模の転職エージェントは経営資源が少ないので、企業として業種、職種、年代、地域などでターゲットを絞り、専門性を強みにしています。
ターゲットの絞り方は様々ですが、これを特化型と呼んでいます。
特化型転職エージェントでは、IT業界・金融業界といった業種、エンジニア・経理といった職種、第二新卒・20代・30代・管理職といった年代やポジション、関東・東海・関西といった地域といった切り口で、専門性を高めています。
総合型と特化型に優劣があるわけではありません。とはいうものの、あつかう求人の情報量は、圧倒的に総合型転職エージェントの方がが多くなります。
例えば、IT業界に特化した転職エージェントは何社もありますが、実際にIT業界の求人情報量が一番豊富な転職エージェントは、業界最大手のリクルートエージェントと言われています。
【仕組み解説5】転職エージェントの利用方法、利用の流れは?
転職エージェントを利用するには、登録が必要です。登録は、転職エージェントの公式サイトにアクセスして、登録ページの入力フォームにプロフィールや希望条件などの情報を入力します。
転職エージェントの登録について詳しくは、次の記事をご覧ください。
転職エージェントに登録後、求職者は転職の専門家であるキャリアアドバイザーと、対面形式あるいは電話などの非対面形式で面談します。
面談後、求職者の経験・スキルや希望を把握したキャリアアドバイザーから、求人の紹介や転職活動のサポートが受けられるようになります。
求人を紹介されたら、興味がない求人は断り、希望がかなう求人があれば応募し、面接、内定、転職とすすみます。
転職エージェントを利用する場合と利用しない場合の大きな違いは、転職エージェントを利用する場合は、内定が出るまで、求職者と求人企業が直接コミニュケーションすることが殆ど無いことです。
求職者と求人企業が直接会話するのは面接の場ぐらいのもので、それ以外の求人企業との連絡や交渉などは全て転職エージェントが介在することになり、求職者の肉体的・精神的負荷は軽減されます。
転職エージェントを使って転職活動を進める場合の、転職の流れをまとめると次のようになります。
- 転職エージェントの利用から転職までの流れ
-
- 転職エージェントの選択
- 転職エージェントに登録
- 転職エージェントと面談
- 転職エージェントから紹介された求人に応募
- 応募した企業・組織と面接
- 応募した企業・組織に内定
- 応募した企業・組織に転職(入社)
上記を例に、先ず転職活動を始めてから内定までに必要な期間についてお話しすると、企業・組織への転職では「6.応募した企業・組織に内定」までに、少なくとも1ヶ月程度の期間が必要になると考えておきましょう。すんなり内定が出た場合の例なので、もう少し時間がかかるケースも出てきます。
転職(入社)までに必要な期間は、組織によって、人によって違い出てくるところです。この点にご留意ください。
円満退職を前提とする場合、内定が出た後、勤務先に退職の意思を伝えてから「7.応募した企業・組織に転職(入社)」までに、1ヶ月程度の期間を設けるのが常識的なところだと思います。よって、転職活動期間は次のように認識してください。
- 転職活動期間
-
企業・組織への転職は少なく見積もっても、転職活動をはじめてから実際に転職するまでに、2ヶ月程度の期間は必要です。
転職エージェントの利用の流れについて詳しくは、次の記事をご覧ください。
【仕組み解説6】転職エージェントを利用するメリットは?
転職エージェントのキャリアアドバイザーは、求職者の経歴やスキル、希望条件を把握した上で、公開求人のみならず非公開求人も含めた数多くの求人の中から、求職者にフィットする求人を探しだし紹介してくれます。
キャリアアドバイザーはその他にも、転職先の内情など独自情報の提供や各種アドバイス、面接対策、交渉代行などで利用者の転職活動を支援します。
転職エージェントを利用するメリットを整理すると、次の通りです。
- 1.豊富な求人の中からフィットする求人を探し出し、紹介してくれる
- キャリアアドバイザー(担当者)は求職者の経歴や経験・スキル、希望を確認し、幅広い求人の中から、求職者にフィットする求人を探し出し、紹介してくれます。求人の中には、求職者が未経験の業界も含まれていることがあり、自分では見つけにくい・気づきづらい転職の可能性を見出してくれるのです。
- 2.求人の背景や職場環境など、表に出てこない独自情報を提供してくれる
- なぜ求人が出ているのかその理由や背景、職場の雰囲気や上司の人柄、過去に採用された人物像や採用理由など、一般に入手しづらい求人企業の情報を提供してもらえます。
- 3.自己PRや志望動機、応募書類作成についてアドバイスしてくれる
- はじめての人には少し面倒な自己PRや志望動機を一緒に整理して考えてくれたり、書類選考が通過しやすくなる履歴書、職務経歴書の書き方などのアドバイスがもらえます。
- 4.模擬面接の実施、面接傾向の助言などの面接対策をしてくれる
- セミナーや模擬面接による面接対策の実施、過去に求人企業の面接で出た質問傾向の助言、面接官に関する情報の共有など、面接を有利にすすめられる支援が受けられます。
- 5.給料・年収などの待遇交渉や、面接などの日程調整を代行してくれる
- 求人企業との面接の日程調整、待遇面の交渉、入社予定日の調整など、転職エージェントが求職者と求人企業の間に入って調整・交渉し、取りまとめてくれます。
- 6.書類選考や面接で落とされたら、その理由を教えてくれる
- キャリアアドバイザーから書類選考や面接で落とされた理由を教えてもらえるので、その後の転職活動を改善できます。キャリアアドバイザーと信頼関係が構築できていれば、かなり具体的に教えてもらえることもあります。
私自身の転職活動を振り返ってみて、転職を成功させるために大切だと思うことは、可能な限り多くの求人情報をあつめて、その中から経歴や希望にあう求人を見つけたらどんどん応募し、その他の部分は極力効率化・省力化すること。
そして内定を得るだけでなく、次のような転職先の具体的な情報を集めて、転職することで今ある問題が解決できるのか・将来の希望がかなうのかを可視化し、未来を変える・夢を実現することにつながる転職かを見極めて判断すること。
- 転職先の仕事内容や待遇・福利厚生
- 転職先の仕事に対する姿勢・考え方
- 転職先で求められている人物像
- 転職先の休日や勤務時間の実態
- 転職先で上司となる方の人柄や職場の雰囲気
転職を成功させるために必要な情報を収集するにあたっては、個人の力だけではどうしても限界があり、求人を出している企業や組織の広く・深い情報が集まってくる環境をつくることが大切です。
この環境を実現するものが、転職エージェントが提供する転職支援サービスであり、限られた時間の有効活用から転職成功へとつなげるためには、転職エージェントの利用・活用が不可欠であると転職マネージャーは考えます。
【仕組み解説7】転職エージェントを利用するデメリットとは?
転職エージェントのメリットをご紹介したので、デメリットや注意点についてもお伝えします。
転職エージェントを運営する人材紹介会社はサービス業ですから、提供する人によってサービスレベルに多少の差が出ることは想定しておかなければなりません。
例えば、キャリアアドバイザーが連絡を怠る等、人に起因する問題が出てくることがあります。転職マネージャーも中規模の転職エージェントを利用した際に経験しました。
私の経験も含めて、具体的な注意点としては、次のようなものがあります。
- 注意すべき転職エージェント
-
- 利用者の質問やメールに対する、回答や返信などのレスポンスが遅い
- 利用者に求人を紹介する際、求人内容を把握していない言動が見受けられる
- 利用者の経歴や希望条件、転職理由を理解せずに、的外れな求人を紹介してくる
- 利用者が興味がないと伝えた求人を、何度もすすめてくる
万が一、このような人材紹介会社の社員と遭遇したら、相手にせず距離を置きましょう。
人材紹介会社の事業は、利用者が転職することで成功報酬が入る仕組みになっています。
滅多にないことですが、自分の成果に結びつけるため・効率化のために、なりふり構わず行動する社員・不誠実な対応をする社員が、中にはいるのです。このような転職エージェントの意見や助言を真に受けて転職活動を進めても、良い結果は得られません。
最悪の場合、転職に失敗し、後悔することになります。
- 転職の失敗例
-
- 転職前よりも労働条件が悪くなってしまった
- 希望がかなわない、理想とは程遠い転職先だった
- 悩みや不安、不満など転職に思い至った問題が解決できない転職になってしまった
このようなリスク予防策として、社員教育・育成に注力しサービスや能力の標準化につとめる、コンプライアンス(法令遵守)意識が高い人材紹介会社を利用することが大切になってきます。
また、万が一問題が起こってしまった時の対策として、利用者の希望によりキャリアアドバイザーを変更できる制度を設けている人材紹介会社もあります。実際に利用することは先ずない制度ですが、このような制度があれば安心につながりますね。
安心して利用できる高評価の転職エージェントについては、次の記事でご紹介しています。
【仕組み解説8】転職エージェントが無料で利用できる仕組みとは?
さまざまな面から転職活動を支援してくれる転職エージェントですが、利用料などの料金は掛かりません。無料で利用できます。
転職エージェントの報酬の仕組みを、裏事情も含めて簡単にご紹介します。求職者の転職が成功すると転職エージェントは、求職者を採用した企業や組織から成功報酬をもらうことになっています。
その額は、転職エージェントによって多少の違いはありますが、転職した人がもらう年収の20〜30%相当です。もちろん、求職者の年収から成功報酬が差し引かれるわけではありませんので、ご安心ください。
このような仕組みによって、求職者は便利な転職支援サービスを無料で利用できるのです。
なお、法律上も、転職エージェントは、原則として求職者から手数料や報酬を受けとれないことになっています(参考:厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」)。
また、転職エージェントには、転職した人が数ヶ月といった短期間で退職してしまうと、受け取った成功報酬の何割かを、採用した求人企業に返金する返戻金の制度があります。
そのため、目指すことは求職者、求人企業、転職エージェントの三者が満足する転職。転職エージェントの社員は、求職者の経歴・希望条件と、求人企業の要望・要件がマッチする求人を探しだし、求職者にフィットする求人を紹介するよう努めます。
求職者にとっての転職エージェントとは、求人企業に対してご自身を共に売り込んでくれるパートナーと考えると良いでしょう。
【仕組み解説9】転職エージェントに利用を断られることがあるの?
無料で利用できる便利な転職エージェントですが、転職エージェントがサービスを提供できないケースもあります。転職エージェントに登録した方の、経歴やスキル、希望条件に合う求人をあつかっていない場合に起こります。
実際、私も30代後半の転職活動では、10社以上の転職エージェントに登録しましたが、うち2社から「ご紹介できる求人案件がございません」といった内容のメールが届きました。
これを受けて、転職エージェントに断られる、登録拒否されると言う方もいますが、正確に言うと転職エージェントは断ったり、登録を拒否したわけではありません。
転職エージェントが企業から預かっている求人の中で、求職者にフィットする求人が見つからず、転職エージェントから求職者に紹介できる求人が無いことを連絡してます。
裏事情も補足しますと、職業安定法(第5条の6)により、転職エージェントは原則、求職の申し込みを全件受理しなければなりません。
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
紹介できる求人がないと言われると、自分の価値を否定されるようで少しショックですが、その転職エージェントに限っての話なので気にしないようにしてください。私もその後、別の転職エージェントを利用して転職しています。
このような連絡で動揺する時間はもったいないです。新しい転職エージェントの利用を検討しましょう。
利用するメリットが多い転職エージェントですが、ご自身が応募できる求人をあつかっていないのならば、利用する価値はありません。
このようなこともあるので転職エージェント利用にあたっては、業種や職種、年代、地域など、各転職エージェントの得意・不得意といった特徴を知っておくことが大切です。
当サイトでおすすめする転職エージェントの特徴については、次の記事でご確認いただけます。
当サイトがおすすめする転職エージェントの公式サイトは、こちらからご覧になれます。
あとがき:転職エージェントの仕組み【無料の理由、転職支援の内容など裏事情を含む9項目から解説】
この記事では、次の9つの項目から、転職エージェントの基本的な仕組みを解説しました。
- 転職エージェントが提供する転職支援サービスとは?
- 転職エージェントが紹介する求人の特徴とは?
- 転職エージェントのキャリアアドバイザーとリクルーティングアドバイザーの役割は?
- 転職エージェントの運営体制は?
- 転職エージェントの利用方法、利用の流れは?
- 転職エージェントを利用するメリットは?
- 転職エージェントを利用するデメリットとは?
- 転職エージェントが無料で利用できる仕組みとは?
- 転職エージェントに利用を断られることがあるの?
記事を読んだら、転職エージェントがご自身に向いているサービスか整理して、転職エージェントの利用を判断してみてください。
最後にこの記事と同じ、正社員の転職ノウハウ・知識に関する記事をご紹介します。
転職活動でたくさんのよい出会いがありますよう、お祈りいたします!