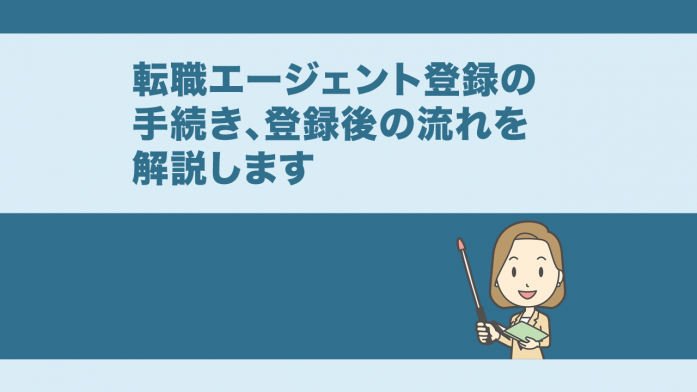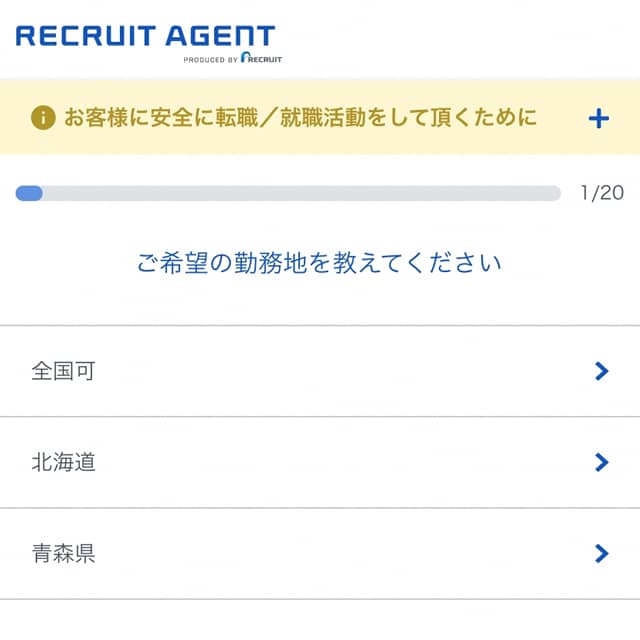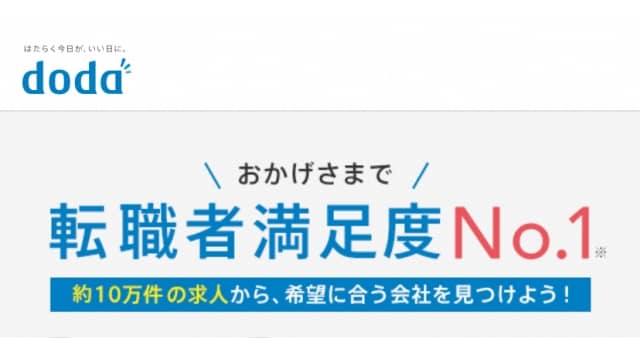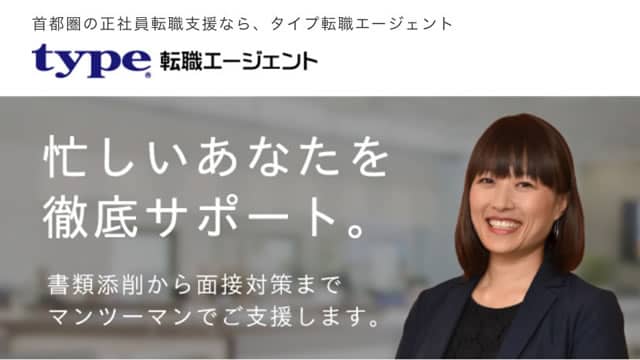転職エージェントの利用をお考えの方に、利用にあたって必要となる転職エージェント登録の手続き、登録後の流れをを解説します。
- 転職エージェントに登録する時期は、いつごろがいいの?
- 転職エージェントに、どんな情報を登録するのか教えて!
- 転職エージェントに登録する時に、職務経歴書は必要なの?
- 転職エージェントの登録にかかる時間は、どのくらい?
- 転職エージェントに登録した後は、何をするの?
はじめて転職エージェントに登録する方は、登録する個人情報や作業量、登録後の流れは気になるところだと思います。
この記事では、私の経験もふまえて、転職エージェントの登録時、そして登録してから転職エージェントの初回面談までに必要となる準備や作業をご紹介しながら、注意点やアドバイスをお伝えします。
それでは、転職エージェント登録の6つのポイントから見ていきましょう。
目次
転職エージェント登録の6つのポイント
転職エージェントを利用するには、転職エージェントに登録する必要があります。転職エージェントの登録について、次の6つのポイントから解説します。
- 転職エージェント登録の流れ
- 転職エージェントの登録にかかる時間
- 転職エージェントに登録する時期
- 転職エージェントの登録数
- 転職エージェントの登録が怖い、利用に不安がある場合
- 登録すべき転職エージェント6選
転職エージェント登録の流れ
転職エージェント登録の流れは、先ず転職エージェントの公式サイトにアクセスして、次に登録ページの入力フォームにプロフィールや職務経歴(簡単な職務内容)、希望条件などの情報を入力する、といったものになります。上記画像は、リクルートエージェントの登録ページの例です。
入力後、登録ページの最後にある登録用のボタンを押すと、入力した情報が転職エージェントに登録されます。裏を返せば、登録用のボタンを押さなければ、入力した情報が転職エージェントに登録されることはありません。
- 転職エージェント登録の流れ
-
- 転職エージェントの公式サイトにアクセス
- 転職エージェントの登録ページの入力フォームに情報を入力
- 転職エージェントの登録ページの最後にある登録ボタンを押す
転職エージェントによって多少の違いはありますが、登録する情報は、次のようなものです。
- プロフィール
-
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- メールアドレス
- 電話番号
- 住所
- 最終学歴
- 保有資格
- 語学力
- 職務経歴
-
- 離職中・在籍中といった現在の就業状況
- 経験社数
- 直近の勤務先企業名
- 勤務期間
- 雇用形態
- 業種
- 職種
- 役職
- 年収
- 職務内容
- 希望条件
-
- 転職希望時期
- 希望勤務地
- 希望職種
登録ページに入力するだけなので作業自体は簡単ですが、ちょっとだけ面倒なのが上の例で言うと職務経歴(簡単な職務内容)の入力です。職務経歴の入力が面倒に感じる理由は、思い出したり、振り返ったりといった記憶を引き出す作業が必要となるからです。
面倒とは言っても、新卒入社から振り返って、いつ、どこの部署で、どのような仕事をしてきたか、箇条書きレベルで業務の棚卸しが出来ていれば問題ないのですが・・・。職務経歴で入力する情報は、実際の職務経歴書のようなきちんとしたものではなく、職務経歴書の簡略版だと思ってください。
なお、業務の棚卸しのやり方について確認しておきたい方は、次の記事をご覧ください。
また、転職エージェント登録時に職務経歴書の提出を求める一部転職エージェントがありますが、職務経歴書の提出は必須ではなく任意のところが殆どです。職務経歴書ができ上がっている人だけ登録すれば良いのです。
チョッとわかりにくく、勘違いする方もいそうなので補足しました。転職エージェントで職務経歴書が本当に必要になるタイミングは、初回面談の時になります。
転職エージェントの登録にかかる時間
実際の転職エージェント登録にかかる時間は、どの程度になるのかご紹介します。
最近の大手転職エージェントの傾向として、登録ページで入力する情報量は、以前と比べて減っています。入力する情報量が少ない転職エージェントであれば、入力必須項目が10項目程度しかなく、職務経歴の入力もかなり省かれているので、登録作業は3分もかかりません。
一般的な転職エージェントの入力必須項目は20〜25項目程度で、簡単な職務経歴の入力が必要となり、10分程度の時間は必要になります。
先ほどご紹介した業務の棚卸しができていれば、登録にかかる時間は短くなります。
ちなみに、前述した「転職エージェントに登録する情報」の例は、20項目を少し超える数になりますので、一般的な転職エージェントの登録ページに入力する情報量の目安になるでしょう。
転職エージェントの登録ページにある、一時保存機能という便利な仕組みをご紹介します。一時保存機能とは、登録手続きを途中で止めても、時間を置いてから登録手続きを再開できるもので、まとまった時間が取れない、スキマ時間にちょこちょこ登録したいという方にとって助かる仕組みです。残念ながら、全ての転職エージェントにある仕組みではありませんが・・・。
例えば、最大手転職エージェントのリクルートエージェントでは、一定の期間内であれば、リクルートエージェントが指定するページで登録メールアドレスを入力することで、前回入力情報を呼び出し、登録手続きが再開できるようになっています。
転職エージェントに登録する時期
転職エージェントを利用して転職活動を進める場合、転職活動を始めてから実際に転職するまでに、少なく見積もっても2ヶ月程度の期間は必要です。
逆算すると、遅くとも転職したいタイミングの2ヶ月前には、転職エージェントに登録しておく必要があります。
転職活動は、日程調整がスムーズにいかないこともあるので、転職エージェントに登録する時期は、少し余裕を持って転職したいタイミングの3ヶ月以上前には登録するのが良いでしょう。
転職エージェントを利用する転職活動の流れや手順の詳細については、次の記事をご覧ください。
転職エージェントの登録数
今すぐ仕事を辞めたい・今すぐ転職したい方と、転職エージェントに登録だけして情報を集めたい・転職相談をしたい方、それぞれにおすすめする転職エージェントの登録数をお伝えします。
今すぐ仕事を辞めたい・今すぐ転職したい方
今すぐ仕事を辞めたい、今すぐ転職したいという方は、複数の転職エージェントを利用して、求人の量を確保することが大切です。
転職エージェントは無料で利用できるので、できるだけたくさんの転職エージェントに登録しても良いのですが、在職中の方が自由にできる時間は限られてくるでしょう。
そこで、在職中の方は、先ず転職エージェント2〜3社に登録し、転職活動を始めてください。
複数の転職エージェントに登録した後、紹介される求人を見て、量が少ない、体力的に余裕がある、応募したい求人が少ないと感じたら、登録数を増やしていきましょう。
退職が決まっている方、離職中の方は、なるべく多くの転職エージェントに登録して、求人情報が集まる環境をつくることが大切です。
そして、より多くの求人に応募し、1日も早く転職を成功させてください。
転職エージェントに登録だけして情報を集めたい・転職相談をしたい方
転職エージェントを利用する方の中には、すぐに転職したいわけではなく、転職エージェントに登録だけして求人や転職市場の情報を集めたい、転職エージェントに転職相談したいという方もいらっしゃいます。
このように転職を急いでいない方は、大手転職エージェント1社に登録すれば十分です。「大手」と書いた理由は、次の通りです。
- 転職エージェントに登録だけして情報を集めたい・転職相談をしたい方が、大手転職エージェントを使うべき理由
-
- 大手転職エージェントは、利用する求職者、求人企業の数が多いので、求人・求職といった最新の転職市場動向に関する情報が集約されるため
- 大手転職エージェントは、これまでの転職支援実績が桁違いに多いので、さまざまな業種、職種、地域の転職に関するデータやノウハウが蓄積されているため
情報収集、相談が主目的であるならば、迷わず大手転職エージェントを利用してください。その後、転職意欲が高くなってきたら登録数を増やして、より多くの求人情報を集め、転職活動を本格化させましょう。
大手転職エージェントについて詳しくは、次の記事をご覧ください。
なお、転職エージェントの登録ページや転職エージェントの初回面談で、転職希望時期を確認されると思います。その際、転職エージェントに対しての回答は、転職希望時期は1年後、あるいは未定のように、転職を急いでいないことを伝えてください。
また、転職エージェントに登録だけして情報を集めたい方の中に、誤解している方がいるので補足します。
転職エージェントと面談をしないと、転職エージェントのWebサイトに公開されている情報しか見ることができません。すなわち、転職エージェントに登録していない人と、入手できる情報が同じということなります。
非公開求人の情報、興味のある業界情報、転職市場の最新動向を得ようと思ったら、面談だけはしておきましょう。面談は対面形式だけでなく、電話面談、Web面談も可能です。電話面談、Web面談であれば1時間もかかりません。
転職エージェントの登録が怖い、利用に不安がある場合
当サイトでは、転職エージェントの登録が怖い、転職エージェントの利用に不安があるという方には、大手転職エージェントの利用をおすすめしています。
大手転職エージェントには、中規模・小規模の転職エージェントに比べて次のような強みがあり、はじめて転職活動する方も、不安なく活動を進めることができるはずです。
選択肢が広がる、大手転職エージェントの転職支援サービス
大手転職エージェントには、さまざまな業種・職種の求人が豊富にあり、幅広い選択肢を提供します。
また、現在お住まいの地域に転職したい方だけでなく、Uターン転職、Iターン転職、Jターン転職、上京転職、都市部への転職を考えている方もいるでしょう。このような転職ニーズに対応するには、全国各地に拠点がある大手転職エージェントが保有する求人情報量や営業力が必要となります。
レベルが高い、大手転職エージェントの転職支援サービス
大手転職エージェントは、利用する求職者、求人企業の数が多いので、最新の転職市場に関する情報やデータが集約されています。
転職支援実績が桁違いに多いことも大手転職エージェントの特徴のひとつで、経験・ノウハウ・スキルなどの転職に関するナレッジが蓄積され、これらの情報は利用者の転職支援に活用されています。
安心・安全な、大手転職エージェントの転職支援サービス
大手転職エージェントはサービス、コンプライアンスなどの社員教育に力をいれ、プライバシーマークを取得するなど個人情報保護にも細心の注意を払っている企業が多いものです。
加えて、少人数の人材紹介会社では対応できない、担当社員を変更できる制度を設け、利用者との相性などの問題が発生した場合の対策を講じるなど、安心・安全なサービスを提供しています。
転職エージェントを利用したいのに、なかなか行動に移せない方は、次の記事もチェックしてみてください。
この後は、大手転職エージェントを具体的にご紹介します。
登録すべき大手転職エージェント6選
当サイトが厳選した、登録すべき大手転職エージェントは、次の6つになります。
- 登録すべき大手転職エージェントNo.1:リクルートエージェント
- 登録すべき大手転職エージェントNo.2:マイナビエージェント
- 登録すべき大手転職エージェントNo.3:JACリクルートメント
- 登録すべき大手転職エージェントNo.4:dodaエージェントサービス
- 登録すべき大手転職エージェントNo.5:パソナキャリア
- 登録すべき大手転職エージェントNo.6:type転職エージェント
登録すべき大手転職エージェントNo.1:リクルートエージェント
- リクルートエージェントの転職支援サービス
-
リクルートエージェントは、20代・30代・40代の幅広い年代の求人を豊富にあつかい、一般職・スタッフ層から、専門職・スペシャリスト、管理職・役職者、エグゼクティブ・経営幹部まであらゆる役職・ポジションの求人に対応する、業種、職種、年代を問わずオールラウンドに強い最大手転職エージェント。売上高、転職支援実績ともにNo.1で、莫大な転職ノウハウが蓄積されています。
- リクルートエージェントの求人が豊富なエリア
-
- 北海道
- 東北
- 関東
- 甲信越
- 東海
- 北陸
- 関西
- 中国
- 四国
- 九州
- リクルートエージェントの評判に関する記事
- リクルートエージェントの公式サイト
登録すべき大手転職エージェントNo.2:マイナビエージェント
- マイナビエージェントの転職支援サービス
-
マイナビエージェントは、20代・30代の求人に強く、幅広い業種・職種に対応、若年層・第二新卒の転職では、最も成果が期待できる転職エージェント。求職者の希望と意思を尊重する姿勢を貫いており、利用する方は主体的に転職活動を進めることができます。
- マイナビエージェントの求人が豊富なエリア
-
- 北海道
- 東北
- 関東
- 東海
- 関西
- 九州
- マイナビエージェントの評判に関する記事
- マイナビエージェントの公式サイト
登録すべき大手転職エージェントNo.3:JACリクルートメント
- JACリクルートメントの転職支援サービス
-
JACリクルートメントは、30代・40代の求人に強く、スキルや技術を活かせるプロフェッショナルの求人、高い職位の求人、高年収の求人を探している人の心強い味方になってくれる、ハイキャリア層専門の転職エージェント。エグゼクティブ(経営幹部)求人案件の対象となる方には、エグゼクティブ専門の人材紹介サービス「JAC Executive」の求人が、あわせて紹介されます。
- JACリクルートメントの求人が豊富なエリア
-
- 関東
- 甲信越
- 東海
- 関西
- 中国
- 海外
- JACリクルートメントの評判に関する記事
- JACリクルートメントの公式サイト
登録すべき大手転職エージェントNo.4:dodaエージェントサービス
- dodaエージェントサービスの転職支援サービス
-
dodaエージェントサービスは、20代・30代の求人に強い、売上高2位の大手転職エージェント。さまざまな業種、職種の、一般職・スタッフ層から、専門職・スペシャリスト、管理職・役職者、エグゼクティブ・経営幹部まで幅広い求人を豊富にあつかっています。
- dodaエージェントサービスの求人が豊富なエリア
-
- 北海道
- 東北
- 関東
- 甲信越
- 東海
- 北陸
- 関西
- 中国
- 四国
- 九州
- dodaエージェントサービスの評判に関する記事
- dodaエージェントサービスの公式サイト
登録すべき大手転職エージェントNo.5:パソナキャリア
- パソナキャリアの転職支援サービス
-
パソナキャリアは、20代・30代・40代の幅広い年代の求人に強く、さまざまな業種、職種の求人に対応する、人材サービス業界大手パソナグループの転職エージェント。応募書類添削、面接対策などの転職支援サービスが充実しています。
- パソナキャリアの求人が豊富なエリア
-
- 関東
- 東海
- 関西
- 中国
- 九州
- パソナキャリアの評判に関する記事
- パソナキャリアの公式サイト
登録すべき大手転職エージェントNo.6:type転職エージェント
- type転職エージェントの転職支援サービス
-
type転職エージェントは、IT業界、通信業界、Web業界、コンサルティング業界の求人に強い転職エージェント。あつかう求人の主なエリアは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県で、20代・30代の求人が豊富に揃っています。
- type転職エージェントの求人が豊富なエリア
-
- 関東
- type転職エージェントの評判に関する記事
- type転職エージェントの公式サイト
転職エージェント登録後にやる4つのこと
転職エージェントに登録した後は、転職エージェントのキャリアアドバイザーと面談することになります。ここでは、転職エージェント登録後にある面談までに準備することについて、解説します。
キャリアアドバイザーは、求職者の転職支援を担当する人材紹介会社の社員です(コンサルタント、キャリアパートナーなど別の呼称を使う人材紹介会社もあります)。
キャリアコンサルタントという名称もありますが、キャリアコンサルタントはキャリアコンサルティングの国家資格を持つ人だけが名乗れます(参考:厚生労働省「キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント」)。キャリアコンサルタントの資格を持つ、人材紹介会社の社員もいます。
転職エージェントに登録後、転職エージェントとの面談の日程調整に関するメールが送られてきますので、希望日を回答します。
ちなみに、面談は土曜、日曜も対応可能な転職エージェントもあります。面談方法も対面方式のみならず、電話面談、Web面談なども選べます。
殆どの転職エージェントは、この初回面談までに職務経歴書と履歴書(キャリアシート)を用意するように連絡してきますので、いわゆる応募書類が必要となるのがこのタイミングです。
とはいうものの転職活動が初めての方は、完成形の応募書類をつくる必要はありません。空欄があっても良いのです。
転職エージェントが面談を設定する目的は、求職者の経歴、希望条件、転職理由などの把握であり、企業との面接のように選考を目的とするものではありません。
面談後、求職者を売れる人材に磨き上げることも、キャリアアドバイザーの仕事の一部です。ですから、職務経歴書や履歴書(キャリアシート)を提出するものの、これら応募書類は面談でキャリアアドバイザーの助言をもらいながら加筆修正できますし、面談後もメールや電話のやり取りで応募書類への助言はもらえるので、安心してください。
既に転職経験がある方は、準備万端で転職エージェントとの面談に臨む方が無難です。準備万端はチョッと言い過ぎかもしれませんが、経験者なのですから以前使用した職務経歴書や履歴書(キャリアシート)をたたき台にして、完成形に近い応募書類を提出するようにしましょう。
それでは、次の4つのことについて、要点を確認していきましょう。
職務経歴書の作成
転職エージェントの初回面談までに、職務経歴書を用意します。
職務経歴書は転職活動を始めることで、はじめて作る書類になります。フォーマットが自由で個人差が出る書類のため、作成にあたって不安を覚える方がいます。
転職エージェントでは、このような方が安心して簡単に職務経歴書が作成できるツールや、サンプルを掲載しているWebページを用意しており、登録後にツールやWebページの案内があります。
ネット上に、職務経歴書のサンプルがたくさんありますが、先ずは転職エージェントから案内されたものを参考に、職務経歴書を作ってみてください。転職エージェントの職務経歴書サンプルは、成功事例を参考にしたもので、業種、職種、役職ごとにさまざまな種類のものが用意されています。
私の例を少しご紹介します。職務経歴書はWordファイルで作成し、項目は上から順に「職務要約」「自己PR」「職務経歴」「免許・資格」で、「職務経歴」は直近のものから書いていました。印刷するとA4サイズ2枚分になります。
職務経歴書は職種や役職によって書く項目が変わりますので、参考程度にとどめてください。
なお、大手転職エージェントが提供する職務経歴書のフォーマットは、上から順に以下の項目がありました。私のものより項目数が多く、項目の順序も違います。
- 職務経歴書の記入項目
-
- 職務要約
- 職務経歴
- 活かせる経験・知識・技術
- 免許・資格
- 自己PR
職務経歴書の枚数に注意しよう!
社会人歴が長くなると、職務経歴書に盛り込むことも増えてきます。すると簡単に枚数が多い職務経歴書ができあがることに・・・。
私の職務経歴書は当初、A4サイズの紙で4枚分ありましたが、転職エージェントのキャリアアドバイザーの助言を参考に、2枚に削った経験があります。
また、中途採用する側の立場で応募書類を読む機会がありましたが、4枚以上ある職務経歴書はチョッと長いなぁと感じましたし、このような方が面接で冗長な説明や話をすると、仕事の能力に疑問符が付くことになったりします。
枚数に決まりはないですが、職務経歴書が4枚以上になったら少し多いかもしれません。
せっかく転職エージェントを利用するのであれば、職務経歴書は転職の専門家の目でチェックしてもらいましょう。
職務経歴書の書き方を工夫しよう!
職務経歴書には様々な書き方があります。編年体式と呼ばれるものは、職務経歴を年代ごとに順を追って書くもので、ご自身の歴史を書くイメージに近いものです。逆に直近のものから書いていくものが、逆編年体式。キャリア式はこれまでの経歴を職種ごとに分類し、例えば営業、販売促進、商品開発と分けて書くものです。
どれが良いかは、経歴や職種はもちろんのこと、職位・役職や経験年数によっても変わってくるものです。
ちなみに私は、20代の転職活動では編年体式を使っていましたが、マネジメントを経験した30代後半・40代前半の転職活動では逆編年体式に変更しました。理由は直近の経歴をアピールしたかったためです。
職務経歴書に限らず売り込むための資料や書類は、アピールしたい項目を必ず見られるところ、目立つところに持ってくるのが良いと思います。職務経歴書で言えば、冒頭部分ですね。
転職エージェントのキャリアアドバイザーに意見を求めれば、各人にあった書き方を助言してくれるはずですよ。
職務経歴書にマネジメント経験や能力を記入しよう!
30代、40代の転職では、求職者にマネジメントの経験・能力を求める求人企業が増えてきます。20代後半の方でも、一部のベンチャー企業はマネジメント能力を期待します。年代を問わず、マネジメント能力が高いに越したことはありません。
マネジメントとは簡単に言えば、組織として成果をあげるための活動です。なにもリーダーや長が付く役職についている必要はありません。役職がなくても、先輩としてメンバーをまとめ、指導することもあるでしょう。
役職の有無にかかわらず、組織として成果をあげるために、何を・何のために・どのようにやってきたのか、その成果・結果はどのようなものだったのか、そして身についたスキル・ノウハウ・技術・能力はどのようなものなのか整理しておきましょう。
繰り返しになりますが、個人ではなく、チームや部、プロジェクトなどの組織として成果をあげるための活動を振り返って整理してください。
そして、マネジメント経験や能力に関することを、職務経歴書に盛り込みます。例えば「免許・資格」「自己PR」などと同様に「マネジメント」という項目を作っても良いですし、「自己PR」の内容をマネジメント経験や能力をアピールする内容にしても良いでしょう。
自己PRの整理
自己PRは、転職エージェントの初回面談までに用意する、職務経歴書に記入します。
職務経歴書の記入項目の中で、多くの方が手を焼くのが自己PRでしょう。
ここでは、自己PRの整理方法をご紹介します。
キャリア開発には、Will(やりたいこと)、Can(できること)、Must(すべきこと)の3つのポイントから、ご自身のキャリアを分析する方法があります。
転職活動を始めるにあたっても、Will(やりたいこと)、Can(できること)、Must(すべきこと)の3つのポイントを、明確にすることをおすすめします。その上で、自己PRを整理してみてください。
- 自己PR
- 自己PRは、Can(できること)を中心に整理します。もう少し具体的に言うと、ご自身が身に付けたスキルやノウハウ、技術、能力などです。これを求人企業、求人の仕事とのつながりを見出して、ご自身が求人の仕事にフィットする人材であることを、明らかにします。
私の自己PRも、Canが主ですが、Willも従の感覚で盛り込んでいました。Mustを盛り込んだことはありません。
私の自己PRの整理方法をご紹介します。私の自己PRは、次のような文章パターンを決めて、書いていました。
例えば◎◎では、◎◎を実践することで、◎◎の成果につなげることができました。
今後は◎◎を活かして、◎◎していきたいと考えています。
それでは1文ごとに、留意していたことをお伝えします。
- ◎◎を通じて、◎◎が身に付きました。
- この文では、仕事を通して、段階的に、継続的に身に付けたスキル・ノウハウ・技術・能力等をアピールしています。段階的、継続的とは、コツコツと地道に長い間がんばってきたことです。コツコツと地道に身につけたスキル・ノウハウ・技術・能力等は、勤勉な日本人は大好きなのですよ。どんなに大きな成果があっても、偶然・運良く出た成果、会社やブランド力に依存して出た成果は、転職した後に成果を出す確率が低くなるので、採用側には魅力的なものに映りません。
- 例えば◎◎では、◎◎を実践することで、◎◎の成果につなげることができました。
- この文では、上記の「◎◎を通じて、◎◎が身に付きました。」についての実例を書いています。可能な限り5W1H、固有名詞、数字を盛り込んだ、具体的な例を書いていました。自己PRは、短い文章で、良いことしか書いていないので、どうしてもウソっぽく見えてしまいます。具体的な例を書くことで、わかりやすくなるだけでなく、ウソっぽさも消えます。達成した目標や仕事で挙げた成果、人から感謝されたことや褒められたこと、困難を克服したことや問題を解決したこと等の実例を思い浮かべ、整理してみましょう。
- 今後は◎◎を活かして、◎◎していきたいと考えています。
- この文では、仕事のやる気、仕事でやりたいことを書いて、採用担当者にアピールしたいと考えていた箇所です。私の職務経歴書では志望動機を記入していなかったため、自己PRの最後に志望動機につながるような1文を入れました。こういった文をこの部分に入れることが、しっくりこない方は自己PRに徹して、「このように◎◎することを心掛け、成果につなげることを得意としています」のように、冒頭でのアピールを繰り返すことで、記憶に残すことを狙っても良いと思います。
Can(できること)は「業務の棚卸し」と密接なつながりがありますので、「業務の棚卸し」ができていない方は、以下の記事を確認しておきましょう。
また、意外と盲点ですが、職務経歴書全体で自己PRすることも意識してみてください。「自己PR」以外の項目で自己PRしても問題ないのですから。
「職務要約」「職務経歴」といった項目の中にも、自己PRに関係する事実やキーワード、数字を盛り込むことで、自己PRへの信頼性が高まり、印象深く記憶に残りやすい自己PRになるはずです。
履歴書(キャリアシート)の作成
転職エージェントの初回面談までに、履歴書を用意します。
履歴書は新卒採用時に誰もが作成経験があるものですし、事実を記入するだけのものなので、履歴書作成が難しいという話はあまり聞いたことがありません。
大手転職エージェントでは、履歴書のことをキャリアシートと呼び、市販の履歴書と体裁が異なる、転職エージェント独自のフォーマットであるケースが多くなります。転職エージェントは求職者専用のWebページを用意し、求職者は専用のWebページで情報を入力し、キャリアシートを作成します。
この場合、転職エージェント登録時に入力した情報がキャリアシートに反映され、キャリアシートの骨子となる部分は自動的に生成されます。求職者は自動生成されたキャリアシートに、専用Webページから情報を追加して、キャリアシートを完成させることになります。
中規模・小規模の転職エージェントになると、Excelファイル形式などの履歴書(キャリアシート)のひな形を用意し、求職者は指定されたファイルに情報を入力して、キャリアシートを作成します。
市販されている一般的な履歴書(JIS規格)は、上から順に以下の項目があります。
- 履歴書の記入項目
-
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 現住所
- 連絡先
- 電話番号
- メールアドレス
- 学歴
- 職歴
- 免許・資格
- 志望の動機
- 趣味・特技
- 通勤時間
- 扶養家族(配偶者を除く)
- 配偶者
- 配偶者の扶養義務
- 本人希望記入欄
この中で、「志望の動機」「通勤時間」は、応募する企業が決まらないと記入できない項目になります。転職エージェントの初回面談時は、空欄で大丈夫な項目です。
「本人希望記入欄」について補足します。「本人希望記入欄」は、希望の職種や勤務地などを伝える場合に記入するものです。転職にあたって希望条件が無い場合は、「本人希望記入欄」に「貴社の規定に従います」と書いておきましょう。
希望条件がある場合、「本人希望記入欄」にわかりやすく書いておき、転職エージェントの初回面談で説明してください。希望条件の書き方は、「父の介護が必要なため、東京での勤務を希望いたします」のように、先ず理由・背景を書いて、次に希望する条件を書くのが一般的です。
- 本人希望記入欄の例文1(希望条件が無い場合)
- 貴社の規定に従います。
- 本人希望記入欄の例文2(希望条件がある場合)
- ◎◎のため、◎◎を希望いたします。
志望動機の整理
志望動機は、一般に履歴書に記入するものですが、転職エージェントの初回面談までに用意する履歴書に、記入する必要はありません。
転職エージェントの初回面談までに用意するものとしての優先度は低いですが、余裕がある人は希望する企業の求人を想定して、練習として志望動機を書いてみて、面談時にキャリアアドバイザーにチェックしてもらっても良いでしょう。
面談までに整理する必要がない志望動機ですが、情報が錯綜しているところもあるので、転職活動をすすめる上での留意点を補足します。
市販されている履歴書(JIS規格)には、「志望の動機」欄があります。この場合、「志望の動機」欄に志望動機を書きますが、大手転職エージェントの履歴書(キャリアシート)には志望動機の欄が無いところもあります。
この場合、どこに志望動機を書けば良いのかと悩む方もいます。職務経歴書に志望動機を記入すべきでしょうか?
この件は転職エージェントでも、意見が分かれるところです。私の場合、大手転職エージェントのキャリアアドバイザーからは「職務経歴書に志望動機は、書かなくていいですよ」とアドバイスされ、中規模の転職エージェントでは求人に応募する際、「志望動機は、履歴書と職務経歴書の両方に入れください」と修正の連絡が入ったこともあります。
私の対応をご紹介すると、原則として職務経歴書に志望動機は書きません。もちろん、修正依頼があった時には対応しましたが。職務経歴書に志望動機を書かないのは、次のようなことを考えてのことです。
- 職務経歴書を求人ごとに変更する影響
- 志望動機は求人ごとに変えているので、職務経歴書に志望動機を記入するとなれば、求人企業ごとに職務経歴書の変更作業が必要になります。いろいろな版の職務経歴書が存在すると、管理も煩雑になります。うっかりミスによって、A社に提出した職務経歴書に、B社の志望動機が書かれているといった問題も起こりやすくなります。
- 職務経歴書に志望動機を盛り込む影響
- 志望動機を私の職務経歴書に盛り込むためには、何かの項目を削る、フォントサイズを小さくするといった対応が必要です。職務経歴書を2枚におさめるために、すでに4枚あったものを2枚に減らしているため、削れる余地は少なく、さらに文字を小さくすると読みにくくなります。
職務経歴書に汎用的な志望動機を書くという対策も考えられますが、そういう志望動機ならわざわざ書かなくて良いと思います。
求職者が転職エージェント経由で求人に応募する場合、転職エージェントは求職者の長所や強みなどとともに、求人企業の仕事にフィットする人材として推薦します。求人企業の書類選考を代行している転職エージェントもあります。
ですので、転職エージェントが、職務経歴書を含む応募書類に志望動機の記入は不要と言えば、心配しなくて大丈夫です。書類選考を通過すれば、志望動機は面接で必ず聞かれます。次のような整理をして、面接でしっかり伝えましょう。
- 志望動機
- 志望動機は、Will(やりたいこと)を中心に整理します。もう少し具体的に言うと、ご自身の夢や目標、理想などです。これを求人企業、求人の仕事とのつながりを見出して、ご自身が求人の仕事に応募した理由を、明らかにします。
なお、Will(やりたいこと)は、転職理由と密接なつながりがあり、転職理由の整理ができていない場合、志望動機の整理が難しくなることもあります。転職理由は、転職エージェントの面談でも質問されるものなので、転職理由の整理ができていない方は、以下の記事を参考に転職理由を整理しておきましょう。
志望動機は求人ごとに変わるので、自己PRでご紹介したようなパターン化は難しく、一筋縄ではいきません。Will(やりたいこと)が主になりますが、Can(できること)、Must(すべきこと)を盛り込んだ方が、うまく整理できることもあります。
志望動機は、ご自身の夢や目標と、求人企業の強みや特長とを結びつけるなど、個別具体的な整理が必要となるため、上手くまとめられない場合は、キャリアアドバイザーに相談するようにしましょう。
転職エージェントの使い方について詳しくは、次の記事をご覧ください。
あとがき:転職エージェント登録の6つのポイント【登録後にやる職務経歴書、履歴書作成も解説】
この記事では、転職エージェントの利用をお考えの方に、転職エージェント登録のポイントを、次の6点から解説しました。
- 転職エージェント登録の流れ
- 転職エージェントの登録にかかる時間
- 転職エージェントに登録する時期
- 転職エージェントの登録数
- 転職エージェントの登録が怖い、利用に不安がある場合
- 登録すべき転職エージェント6選
あわせて、転職エージェント登録後にやることとして、次の4点をご紹介しました。
案ずるより産むが易しという言葉もある通り、転職エージェントの登録は、やってしまえば何ということもありません。
転職エージェント登録後にある面談までに準備が必要となるものについては、全て自分でやろうとせず、できるところまでやったら、転職エージェントのキャリアアドバイザーの力を借りてください。
最後にこの記事と同じ、正社員の転職ノウハウ・知識に関する記事をご紹介します。
転職活動でたくさんのよい出会いがありますよう、お祈りいたします!